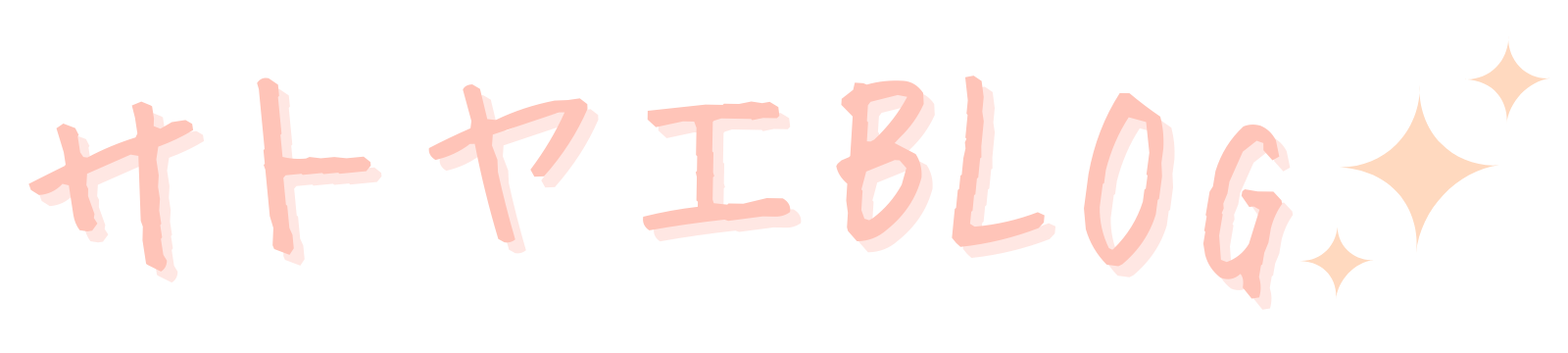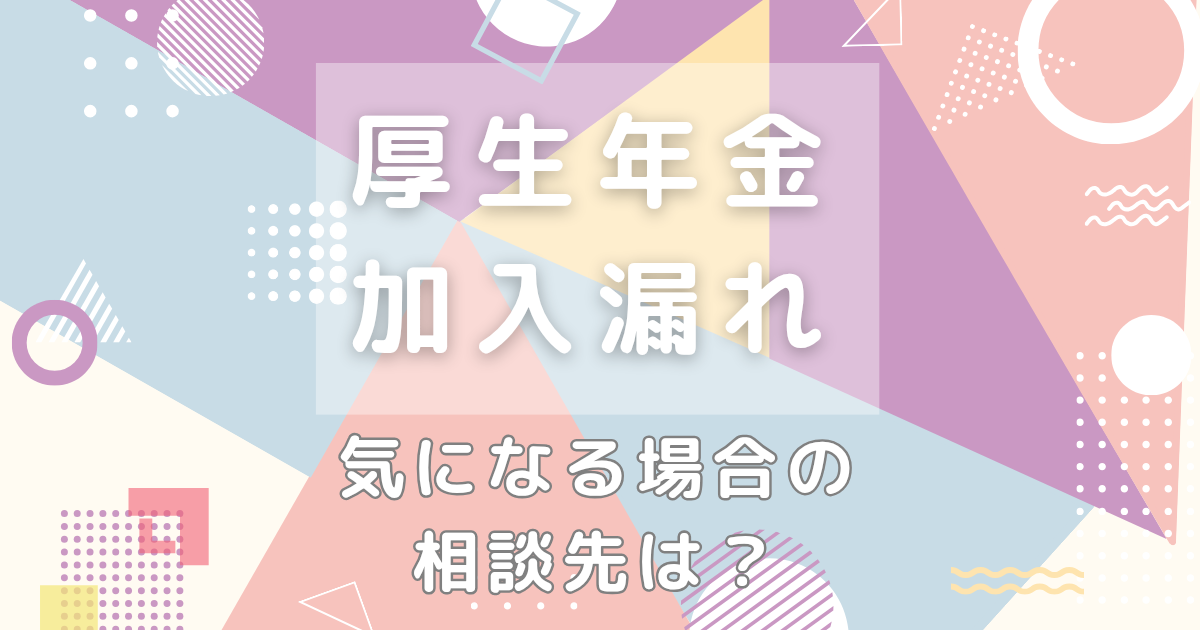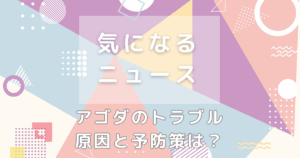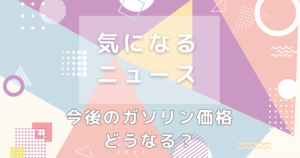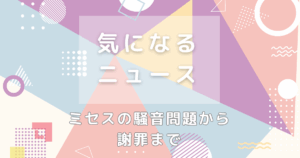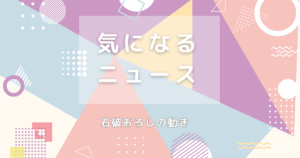厚生労働省の2023年推計によると、厚生年金に加入する資格がありながら国民年金のみに加入している人が約97万人に上ることが明らかになりました。
この背景には、事業者が保険料負担を逃れるために加入手続きを怠るケースが含まれています。
この問題は、将来の年金受給額に大きな影響を及ぼし、老後の生活設計に深刻な問題を引き起こす可能性があります。
この記事では、加入漏れの影響、対策、そして相談先について詳しく解説します。
厚生年金の加入漏れとは?
厚生年金は、会社員や公務員が加入する公的年金制度で、国民年金に上乗せして老後の年金を手厚くするものです。
すべての法人事業所および従業員5人以上の個人事業所(一部業種を除く)に加入義務がありますが、事業者が保険料負担(労使折半、保険料率18.3%)を嫌がり、手続きを怠るケースが後を絶ちません。
厚生労働省によると、2025年3月末時点で約15万事業所が加入逃れの疑いがあるとされています。
加入漏れの原因
- 事業者の負担回避: 保険料は事業者と従業員が折半するため、事業者がコスト削減を目的に加入手続きを怠る。
- 制度の複雑さ: 特に中小企業や個人事業所では、社会保険の手続きに関する知識不足が原因となる場合も。
- 従業員の認識不足: 労働者自身が厚生年金の加入義務を理解していない場合、事業者の不正を見逃してしまう。
もらえる年金への影響
厚生年金に加入していない場合、将来受け取れる年金は国民年金(老齢基礎年金)のみとなり、以下のような影響が出ます。
年金額の減少
厚生年金は報酬比例で計算されるため、加入期間が長いほど受給額が増えます。
加入漏れがあると、老齢厚生年金の部分が受け取れず、年金額が大幅に減少します。
例えば、平均年収500万円で40年間厚生年金に加入した場合、
年額約191万円(老齢基礎年金+老齢厚生年金)を受け取れるのに対し、
国民年金のみでは年額約83万円(2025年度満額)に留まります。
障害・遺族年金への影響
厚生年金に加入していないと、障害厚生年金や遺族厚生年金といった保障も受けられません。
これは、従業員やその家族にとって大きなリスクとなります。
老後の生活設計の不安
年金額の減少は、老後の生活資金不足に直結し、特に物価上昇が進む中で生活が厳しくなる可能性があります。
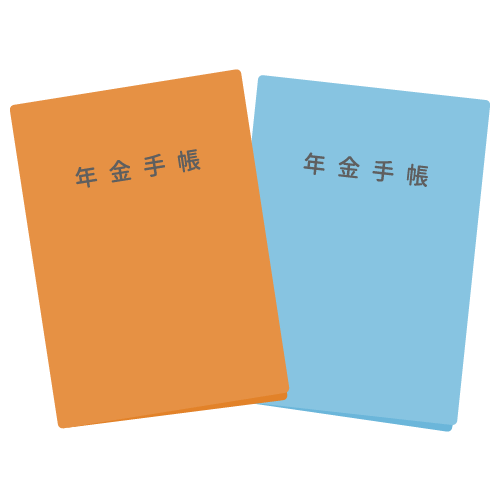
政府・厚生労働省の対策
厚生労働省は加入漏れ問題に対処するため、以下のような対策を進めています。
個人でできる対策
加入漏れに気づいた場合、または疑いがある場合、以下のステップを踏むことが重要です。
①年金記録の確認: 日本年金機構の「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を利用して、自分の年金加入記録を確認しましょう。
20歳以降に未加入期間がある場合、加入漏れの可能性があります。
②事業主への確認: 雇用主に厚生年金への加入状況を確認し、未加入であれば加入手続きを依頼します。
事業主には加入義務があるため、適切な対応が求められます。
③相談窓口への連絡: 事業主が対応しない場合、以下の相談先を利用しましょう。
加入漏れの相談先
加入漏れに関する相談は、以下の機関で受け付けています。
まとめ
厚生年金の加入漏れは、約97万人に及ぶ深刻な問題であり、事業者の保険料負担逃れが主な原因です。この問題は老後の年金額に大きな影響を及ぼし、障害や遺族年金といった保障にも影響します。
政府は適用拡大や指導強化を進めていますが、個人でも「ねんきんネット」での記録確認や相談窓口の活用が重要です。早めに対策を講じることで、将来の生活を守る一歩を踏み出しましょう。
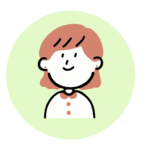 サトヤエ
サトヤエねんきん定期便のチェックは忘れずにしなきゃですね!